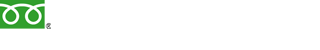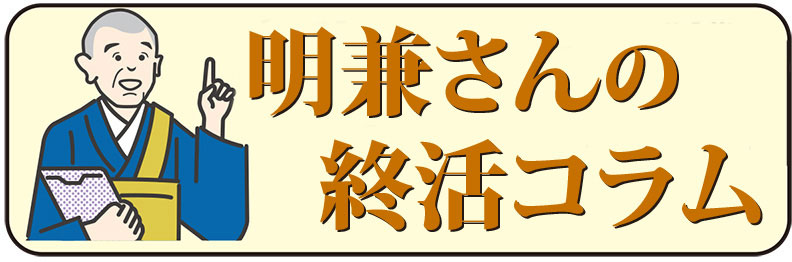40歳で兵庫県の葬祭組合の事務局職員に転職した時に、加盟店の葬儀社の方々に「葬儀の時になんで焼香するのですか?そもそもなんで仏壇で線香を焚くのですか?」と質問したことがあります。様々な説を教えていただきましたが、その時には自分の腑に落ちる答えがありませんでした。葬儀のお勤めにいらした僧侶の方にもお聞きしましたが「食香(じきこう)」のご説明をいただきましたがもうひとつピンときません。時は過ぎて50歳を超えて高野山へ研修という名の“修行”に参加した際、10年間の疑問が綺麗に解決しました。それは仏教がインド発祥の宗教という点に深くかかわりがあります。インドではガンジス川の沐浴は別として、地方に行けば水事情の悪いところが多く、その昔お風呂に入る習慣はありませんでした。体臭も強かったことでしょう。お参りの際に仏様の前に出る時、少しでも良い香りを身にまといたいと、香りの良い植物の樹液を身体に擦り込んだそうです。そうです!お香の根本は身を清めることから始まった作法だったのです。そして貴重な白檀や沈香など洗練された香りが珍重されるようになり、そこからは身を清めることよりも仏様に少しでも良い香りをお届けしたいという「供養」の思いが込められることになります。
先日、ご遺骨の引取りに行ってお勤めしたお宅でも、上記のお話をさせていただきました。読経の際お別れの焼香では私が持参した白檀のお香を焚いていただきました。とても喜んでいただけたと思っております。
写真はクラウドファンディングの返礼品でもお世話になっている高野山の香老舗「大師堂」さんのお香です。黒い容器に入っているのが「塗香(ずこう)」といって手に塗るお香です。お香の原型に最も近いと言えるでしょう。左の容器に入っているのが焼香用のお香でこれは白檀です。とても洗練された涼しい香りがします。香水の成分の中に“サンダルウッド”と記載されているのは実は白檀の事です。線香は白檀の線香と樒の線香です。どちらの線香もとても良い香りがします。皆さんも高野山に行ったらぜひ大師堂さんへお寄りください。
【公式】2万円で安心の散骨、僧侶が供養する海洋散骨代行の明兼坊
#散骨 #墓じまい #大阪湾 #永代供養 #供養 #改葬